神社で行う日本の伝統的な結婚式のことを『神前式』といいます。『神社挙式』、『神前結婚式』とも呼ばれますね。白無垢に赤い紅をさした花嫁姿には、誰でも一度はあこがれたことがあるのではないでしょうか。
以前は結婚式といえばチャペルなどで行う教会式が主流でしたが、近年では結婚式の多様化と共に、神前式を選ぶカップルが増えているようです。
この記事では神前結婚式の歴史や基礎から、神前結婚式の流れ・マナー、新郎新婦・参列者の服装、また神前結婚式を行える神社まで。神前結婚式の情報を幅広くご紹介していきます!

神社で行う日本の伝統的な結婚式のことを『神前式』といいます。『神社挙式』、『神前結婚式』とも呼ばれますね。白無垢に赤い紅をさした花嫁姿には、誰でも一度はあこがれたことがあるのではないでしょうか。
以前は結婚式といえばチャペルなどで行う教会式が主流でしたが、近年では結婚式の多様化と共に、神前式を選ぶカップルが増えているようです。
この記事では神前結婚式の歴史や基礎から、神前結婚式の流れ・マナー、新郎新婦・参列者の服装、また神前結婚式を行える神社まで。神前結婚式の情報を幅広くご紹介していきます!

結婚式といえば以前はチャペルなどで行う教会式のが主流でしたが、時代の流れとともに結婚式も多様化。ゼクシィ結婚トレンド調査2021(LINK)によると、教会式を挙げたカップルは2004年から2021年の間に74.2%から55.9%まで大幅に減少しているようです。
一方で、神前式を選ぶカップルは、8.2%→19.2%まで増加。2倍以上も増えたことになります。(首都圏・リクルート ブライダル総研調べ)
この背景にあるのは価値観の変化と、結婚式の多様化。バブル時代では、華やかなウェディングドレスにド派手な演出。たくさんの参列者に魅せる結婚式が好まれましたが、今では2人の誓いや、大切な家族や友人に感謝を伝えるための場として、アットホームな温かみのある結婚式が好まれる傾向にあるそう。
また需要も多様化する中で、2人だけや家族だけで挙げるのに適した厳かな神社から、大人数で披露宴を行える会場と併設した大規模な神社まであるので、それぞれのカップルの好みに合った神社選びができ、さらに披露宴では和装だけではなくお色直しにドレスが選べるなど、たくさん映えたい令和カップルの需要にマッチ。
このような背景から、神前式を選ぶカップルが増えているようです。

伝統的なイメージのある神前式ですが、実は神社での挙式が広まるきっかけになったのは明治33年(1900年)のこと。皇太子・嘉仁親王(のちの大正天皇)が日比谷大神宮(東京大神宮)で挙げた結婚式がはじまりでした。
100年以上も歴史があるのに、「歴史が浅い」と言われてしまうのも、日本の面白いところですが、それまで結婚の儀礼は各家庭で行っていたため、今の結納に近い形のものが一般的でした。しかし、明治の世になりキリスト文化が輸入されたことから、日本でも神様の前で愛を誓う結婚式の概念が生まれます。そこで、日本の神様を祀る神社でも、新郎新婦・両家の契りを交わす神前式を行えるところが増えていきました。
しかし結婚の儀式自体は歴史が古く、はじめての記録はなんと日本最古の書物・古事記の、神話の時代までさかのぼります。古事記によれば、日本を生んだ夫婦神、イザナキとイザナミは、大きな柱の周りを別々にくるりとまわり、出会ったところで「あら、なんて素敵な男性でしょう」「ああ、なんて素敵な女性なんだ」とお互い声をかけ合ったそう。なんとも可愛らしい結婚の儀式です。
今でも、兵庫県淡路島にある伊弉諾神宮などで、この神話を元にした神前式が行えます。
日本には夫婦円満の御神徳(ご利益)のある神様がたくさんいらっしゃるので、そんな御神徳にあやかれるのも神前式の良いところでしょう。

日本の神様たちは恋愛も大好き。夫婦円満の御神徳がある神様はたくさんいらっしゃいますが、中でも有名な神様を軽くご紹介いたします。
まず、縁結びの神社として最も有名なのは島根県の出雲大社でしょう。年に一回、国中の八百万の神々が出雲に集まり、『ご縁』を決めているという言い伝えが由来です。
出雲大社の御祭神様は大国主大神。古事記にも『麗しき男』と書かれたイケメンの神様です。名前がたくさんあり、大己貴命、大国魂神、大黒様、大物主神(金毘羅さん)など、いろいろな呼び方で親しまれています。恋愛上級者かつ愛妻家の大国主大神に愛を誓うのは安心感がありますね。多くの神社に祀られているので、興味があれば確認してみてください。
他にも、日本で初めての夫婦お多賀様(伊弉諾尊・伊邪那美尊)、新婚生活を喜ぶ和歌を詠った天王様・祇園様(須佐之男命)、この3柱を祀る熊野様、みんなの幸せを願う神明様(天照大御神)、一途な山王様(大山咋神)、愛妻家の八幡様(応神天皇)、子孫繁栄の東照宮(徳川家康公)などなど、ここには書ききれないほど、夫婦円満と家族の幸せを願ってくれる神様がたくさん。
ビビッときた神社の御祭神様を調べてみるのもおもしろいでしょう。神話や由来の中に、夫婦円満のヒントが隠されているかもしれません。
また、基本的には親族のみで行う式のため、参加する機会が少なく、神前式の流れが分からない方も多いのではないでしょうか。
ここでは神前式のおおまかな流れについてご説明します。
神社によって流れが前後したり、略式であったり、
独自の儀礼が入ることもありますので、参考までにご確認ください。

神様の前で結婚のご報告をするので、まずは身を清めます。
やり方は普段神社に参拝するときと同じ方法ですが、新郎新婦共に動きが取りづらい正装のため、巫女さんが手伝ってくれたり、お二人で助け合いながら手水の儀を行うこともあります。

神職さんや巫女さんが先頭に立って、新郎新婦、ご両親、親族の方々を拝殿に案内します。
参進の儀では雅楽が奏でられたり和傘をさしたり、神前式の始まりを告げるのにふさわしく、厳かな空気に包まれます。

拝殿についたら着座します。立ったまま式を行う神社もあります。
神様から向かって左側が新郎、右側が新婦になります。
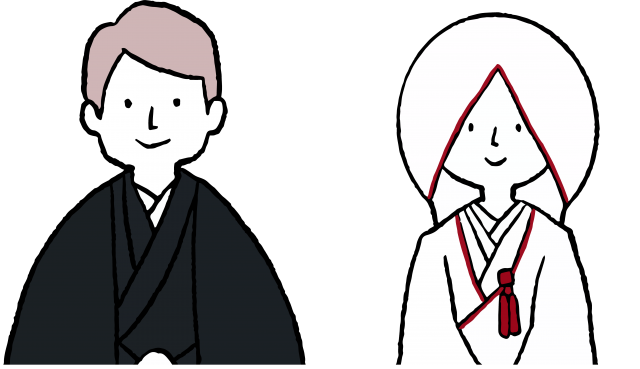
※新郎新婦の位置が逆の神社もあります

修祓(しゅばつ)とは、罪や穢れを祓う儀式のことです。まず、神前式を執り行う神職さん、『斎主(さいしゅ)』が祓詞(はらいことば)をあげます。次に大麻(おおぬさ)を振り、新郎新婦と参列者の穢れを祓います。
参加者の穢れが全て祓われたところからが、神前式のはじまりです。
斎主さんの起立を合図に、指示に従って新郎新婦・参列者全員も起立をします。そして神様に丁寧に拝礼をします。

献饌(けんせん)とは、神様に感謝の気持ちを伝えるため、お供え物を捧げることです。献饌は事前に神職さんが行い、神前式では省略されることも多いです。

斎主さんが祝詞(のりと)を奏上します。ここで神様に2人の結婚のご報告し、末永く幸せであることを願います。

続いて新郎新婦が神前に進み、誓詞(せいし)を奏上します。誓詞奏上では2人から直接神様へ結婚のご報告、家族で苦楽を共にする誓い、どうか見守っていてくださいというお願いをします。

三献の儀とは、三々九度の盃のことです。「夫婦固めの盃」とも呼ばれています。
小中大、三つの杯を使い、三回でお神酒を注ぎ、三回で飲み、新郎新婦合わせて九回お神酒を飲むことから、三々九度といわれるようになりました。
新郎新婦が同じ盃を交わし、同じ盃からお神酒を呑むことで、夫婦として固く結ばれる大切な儀式です。

玉串とは、榊などの枝に紙垂(しで)を結んだものです。今となっては本来の意味は分からなくなってしまいましたが、古事記に元となる記述が残っています。岩屋に隠れてしまった太陽神・天照大御神に出てきてほしいと願い、八百万の神々が榊に紙垂を結んで捧げるなどして、無事に出てきてもらうことができた天岩戸神話です。
このことから、玉串には自分の気持ちを宿し、神様に伝える力があると考えられています。
神様に直接想いを届けることができる、貴重な機会。ぜひたくさんの感謝や願いを込めて神前に捧げてください。

巫女さんや指名したゲストが指輪を運んできます。新郎は新婦の左手薬指に、新婦は新郎の薬指に、指輪をはめます。
祝福のために、巫女さんが舞を捧げます。

ご親族の前に用意された盃に、巫女さんや神職さんがお神酒を注いでいきます。全員にいきわたったら起立し、一緒にお神酒を飲み干します。
これによって両家が親族となり、深く結ばれます。
神様に捧げたお供え物をお下げします。こちらも献饌と同様、神職さんが式の後に行い、略式となることがあります。
神前式を無事に執り納めることができた感謝の気持ちを込めて、拝礼します。斎主さんに合わせて全員で起立をし、神様に深くお辞儀をしましょう。
ここで、斎主さんのご挨拶が入ることもあります。

斎主、新郎新婦、仲人、両親、親族の順番で退場していきます。
折り鶴シャワーや、集合写真など、希望の演出がある場合は、事前に神社に確認してください。また近年人気が高まっている水合わせの儀は、披露宴で行うことが一般的です。

初穂料(祈祷料)の相場は50,000円ほどですが、神社によって違いがあります。30,000~100,000円と幅があり、御祈祷以外のオプションによっても変わりますので、事前に確認をしましょう。
初穂料は当日、受付の時に渡すのが一般的ですが、ウェディング会社を通している場合、直接お渡ししないこともあります。担当の方に確認をしてください。
 初穂料はのし袋に入れて納めましょう。上部に「御初穂料」と書き、下部に自分の氏名を記入します。
初穂料はのし袋に入れて納めましょう。上部に「御初穂料」と書き、下部に自分の氏名を記入します。
ちなみに上部については、「初穂料」「御神前」「御供」「御榊料」「御玉串料」「御神饌料」「奉献」「奉納」「上」と書くこともあります。地域や神社によって違いはありますが、特に決まりを聞いたことがなければ「御初穂料」と書くのが無難でしょう。
のし袋の種類は、蝶結びになっている紅白の水引のついたものをお選びください。お祝い事ですので、水引は少し豪華なものがおすすめですが、印刷でも問題ありません。どうしても用意ができなかった場合でも必ず封筒には入れましょう。お札を裸のまま奉納することは失礼になります。
初穂料は神様への奉納になりますので、できれば新札を用意しましょう。新札が用意できなかった場合は、なるべく綺麗なお札を選びましょう。封筒の中に入れるときは、表側に人物が印刷されている面を向けるのがマナーです。また、のし袋に入れた金額は、内袋かのし袋の裏に記入してください。
新郎新婦のご両親は、母親が黒留袖もしくはアフタヌーンドレス、父親が黒紋付き袴もしくはモーニングコートとなります。
招待された方は、和装でも洋装でも構いませんが、神前で御祈祷を受けるので、基本的には正装もしくは、セミフォーマルな恰好が好ましいです。学生で制服がある場合は、制服が正装になりますので、制服を着ていくのがよいでしょう。
和服の場合、未婚女性は「振袖」か「訪問着」。既婚者は「色留袖」「訪問着」が好ましいです。普段の御祈祷であれば落ち着いた着物が好まれますが、結婚式なので、華やかなお着物でも問題ありません。
洋装の場合も華やかなもので問題ありませんが、あまりにも露出の高い服や派手すぎる装飾品などは、神様に対して失礼になってしまうので避けましょう。
また男性の場合は、正装の黒紋付き袴を着てしまうと、新郎とかぶってしまうので避けましょう。着物を着たい場合は、「色紋付」となります。
主役はあくまでも新郎新婦ですので、考慮しながら服装を選びましょう。
神社は文字の通り「神様のお社」であり、様々な神様が祀られています。神様にはそれぞれの御神徳がありますが、2人の門出を祝ってくれない神様はいません。日本の神様は恋愛も結婚も子孫繁栄もみんな応援してくれます!
お2人がビビッときた神社で素敵なお式を挙げられることを、陰ながらお祈りしております!!
氏神様をお探しの方でわからない場合は、各都道府県の神社庁にお問い合わせください。
| 神社名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北海道神社庁 | 〒064-0959 札幌市中央区宮ヶ丘474-35 | 011(621)0769 |
| 青森県神社庁 | 〒038-0024 青森市浪館前田1-2-1 | 017(781)9461 |
| 岩手県神社庁 | 〒020-0872 盛岡市八幡町13-2 | 019(622)8648 |
| 宮城県神社庁 | 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-9-8 | 022(222)6663 |
| 秋田県神社庁 | 〒010-1427 秋田市仁井田新田2-15-26 | 018(892)7932 |
| 山形県神社庁 | 〒990-0053 山形市薬師町2-8-75 | 023(622)4509 |
| 福島県神社庁 | 〒963-8034 郡山市島1-10-20 | 024(925)0457 |
| 茨城県神社庁 | 〒319-0397 水戸市三湯町1108-300 | 029(257)0111 |
| 栃木県神社庁 | 〒320-0015 宇都宮市八幡台14-24 | 028(625)2011 |
| 群馬県神社庁 | 〒370-0861 高崎市八千代町2-4-26 | 027(326)2274 |
| 埼玉県神社庁 | 〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町1-447-1 | 048(643)3542 |
| 千葉県神社庁 | 〒260-0001 千葉市中央区都町4-3-1 | 043(310)7166 |
| 東京都神社庁 | 〒107-0051 港区元赤坂2-2-3 | 03(3404)6525 |
| 神奈川県神社庁 | 〒235-0019 横浜市磯子区磯子台20-1 | 045(761)6387 |
| 新潟県神社庁 | 〒955-0042 三条市下坂井14-21 | 0256(32)0613 |
| 富山県神社庁 | 〒930-0088 富山市諏訪川原1-10-21 | 076(432)7390 |
| 石川県神社庁 | 〒920-0811 金沢市小坂町西44 | 076(252)7771 |
| 福井県神社庁 | 〒918-8014 福井市花堂中1-3-28 | 0776(34)5846 |
| 山梨県神社庁 | 〒400-0013 甲府市岩窪町572 | 055(288)0003 |
| 長野県神社庁 | 〒380-0801 長野市箱清水1-6-1 | 026(232)3355 |
| 岐阜県神社庁 | 〒500-8384 岐阜市藪田南3-8-24 | 058(273)3525 |
| 静岡県神社庁 | 〒420-0821 静岡市葵区柚木250-2 | 054(261)9030 |
| 愛知県神社庁 | 〒456-0031 名古屋市熱田区神宮1-1-1 | 052(682)8041 |
| 三重県神社庁 | 〒514-0005 津市鳥居町210-2 | 059(226)8042 |
| 滋賀県神社庁 | 〒520-0035 大津市小関町3-26 | 077(524)2753 |
| 京都府神社庁 | 〒616-0022 京都市西京区嵐山朝月町68-8 | 075(863)6677 |
| 大阪府神社庁 | 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺6号 | 06(6245)5741 |
| 兵庫県神社庁 | 〒650-0015 神戸市中央区多聞通3-1-1 | 078(341)1145 |
| 奈良県神社庁 | 〒634-0063 橿原市久米町934 | 0744(22)4731 |
| 和歌山県神社庁 | 〒641-0022 和歌山市和歌浦南3-4-10 | 073(446)5611 |
| 鳥取県神社庁 | 〒680-0015 鳥取市上町87 | 0857(24)7699 |
| 島根県神社庁 | 〒699-0701 出雲市大社町杵築東286 | 0853(53)2149 |
| 岡山県神社庁 | 〒703-8272 岡山市中区奥市3-22 | 086(270)2122 |
| 広島県神社庁 | 〒732-0057 広島市東区二葉の里2-1-1-2 | 082(261)0563 |
| 山口県神社庁 | 〒753-0091 山口市天花1-1-3 | 083(922)0506 |
| 徳島県神社庁 | 〒770-8007 徳島市新浜本町2-3-61 | 088(663)5102 |
| 香川県神社庁 | 〒760-0005 髙松市宮脇町1-30-3 | 087(831)2775 |
| 愛媛県神社庁 | 〒791-0301 東温市南方1954-2 | 089(966)6640 |
| 高知県神社庁 | 〒780-0065 高知市塩田町19-33 | 088(823)4304 |
| 福岡県神社庁 | 〒812-0055 福岡市東区東浜1-5-88 | 092(641)3505 |
| 佐賀県神社庁 | 〒840-0843 佐賀市川原町8-27 | 0952(23)2616 |
| 長崎県神社庁 | 〒850-0006 長崎市上西山町19-3 | 095(827)5689 |
| 熊本県神社庁 | 〒860-0005 熊本市中央区宮内3-1 | 096(322)7474 |
| 大分県神社庁 | 〒870-0047 大分市中島西3-8-19 | 097(532)2784 |
| 宮崎県神社庁 | 〒880-0053 宮崎市神宮2-4-2 | 0985(25)1775 |
| 鹿児島県神社庁 | 〒892-0841 鹿児島市照国町19-20 | 099(223)0061 |
| 沖縄県神社庁 | 〒900-0031 那覇市若狭1-25-11波上宮内 | 098(868)3697 |
